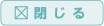★こどもの森です!
今日は寒い!!
新潟に60年余り住んでいますが、今日が人生で一番寒い日かもしれません。
でも考えてみれば、もっともっと寒い北国ウクライナでは、インフラも止められ、爆弾も日常的に落ちてくる・・・そんな日々を送っておられるわけです。
1日も早い戦いの終息を祈らずにいられません。
★さて外来の感染症流行状況です。
1月に入って、コロナは減少してきています。
替わって、インフルAが増加しています。
中心は保育園年齢ですが、小学校・中学校にも見られ始めています。
しかし、コロナ前のようにインフルで学級閉鎖という事態は、今の所、生じていません。
これは、やはりマスクの効果だと思います。
★一方、昨今、「5類」「マスク終わり」の話題が世間を賑わせています。
たしかに現在の「濃厚接触・自宅待機」の制度は、そろそろ時代に合わなくなってきているようにも思います。
3年前のように、コロナがどんな病原体なのかについて、まだまだ知見が少なかった時代で、県内に数えるほどしか患者さんがおられなかった段階では、もちろんとても重要な対策でした。
「リンクが追える」と表現されていた頃です。
しかし現在は状況が全く異なります。
いつでも、だれでも、どこからでも、もらってしまう可能性がある病気になってきています。
★しかし「マスクをやめる」という決断は、全くこれと次元が異なることがらです。
デルタ株よりは軽症が多いとはいえ、毎日コロナ死亡がたくさん報告されています。
取り扱いを緩めて5類にするときこそ、感染対策の重要性を再確認する時だと思います。
★政府は産業界の意向を伺わざるを得ないお立場ですから、仕方ないのかもしれませんが、ノーマスクに舵を切っている欧米を「お手本」とするというスタンスには、明治初期の香りを感じます。
自分の身を守るために、自らマスクを続けるという我が国の意識の高さをこそ、誇るべきかと思います。
これこそが私たち日本人の「民度の高さ」ですから。
★言語習得中の3歳未満のお子さんでは、口元をよく見ることがとても大切ですから、マスクは悪影響が大きいように思います。
また2歳未満児は、呼吸への悪影響も考慮すべきです。
しかしそれ以上の年齢では、この「5類へ」の時期だからこそ、マスクはしっかり続けましょう。
★さて今日の話題は、「子どもたちの脳を健やかに育む食」の提案です。
近年、発達障害と診断されるお子さまがとても増加しています。
その頻度は、6%とも8%とも言われています。
私は5つのこども園・保育園の園医をさせていただいていますが、現場の保育士さんの偽らざる実感として、ざっくり30年前と比べて、ひとりの保育士で担当できる子どもの数が激減したという声をいただきます。
保育にサポートがたくさん必要なお子さんが激増しているというのです。
*落ち着いて作業に集中できない、
*一斉の指示を的確に実行できない、
*お友だちにすぐに手が出てしまう、
*場面の切り替えができない、 などなどです。
★このような傾向のお子さまたちが就学すると、その一部はいわゆる「発達障害」と診断されます。
もちろん的確な薬物治療が必要なお子さまも確実におられます。
しかしその大前提として、生活リズムや食の見直しも、とても大切なように思います。
今回はそのうち「食」に焦点を当てて考えてみましょう。
1)『バランスよく栄養を摂取して代謝を健やかに進ませる』
脳の働きは、神経伝達物質が多くの役割を担っています。
不足や過剰でいろんな症状が出ます。
たとえば・・・
*セロトニン不足:不安、こだわり、イライラ、恐怖、パニック、睡眠障害
*ドーパミン過剰:多動
*ドーパミン不足:脳の誤作動
*ノルアドレナリン、アドレナリン不足:やる気の低下、眠い
などです。
これらの物質は、体の中で複雑な代謝回路で生成されます。
代謝回路は複数が複雑に組み合わさって、全体として機能します。
また代謝は酵素により司られます。
酵素が働くには、ビタミンやミネラルが必須です。
その最も重要なものは、ビタミンBの一種である「葉酸」です。
葉酸は葉野菜に多く含まれます。
そのほかのビタミンB、ビタミンCも大切です。
マグネシウム、鉄、亜鉛、銅なども大切です。
たとえ遺伝的に全く異常がなくとも、上記のように代謝酵素が順調に働かなければ、脳は健やかに育ちません。
日常の暮らしで心がけていただきたい食材は、野菜、果物、穀物、豆類、海藻、種子、魚介、肉 などのバランス良い摂取です。
2)『小麦製品は控えめに』
「リーキーガット」という言葉を聞いたことがありますか?
リーキー=漏れ出る
ガット=腸
「漏れ出る腸」という意味です。
本来小麦は広く人類が食べてきた安全な穀物です。
しかし、人間に好まれるよう品種改良を重ねた結果、本来の小麦よりグルテン含量の多い「ヒトの消化しにくい小麦」となってしまっているのです。
他にも、グルテンの一部のグリアジンが、「ゾヌリン」を分泌させ、これが腸の構造を壊すとも言われています。
このような小麦の性質から、リーキーガット状態になると、未消化の小麦は体内に侵入して抗体を作らせます。
ところで私たちの臓器のいくつかは、その構造がグルテンに似通っているために、作られた抗体が体を攻撃する場合があることが知られています。
パン、お菓子、麺などに多用されている小麦ですが、主食の穀類として常食することは、あまりおすすめできません。
幸い私たち日本人は稲作文化の民族です。
米、米粉などを中心に、時にははい芽米、発芽玄米、雑穀なども取り入れて、健やかな主食を目指しましょう。
3)『化学調味料はなるべく控える』
なかでも「グルタミン酸」の弊害は有名です。
味の素、ハイミー、顆粒の化学調味料にたくさん含まれています。
グルタミン酸ナトリウムは、たんぱく質や他のアミノ酸と結合しないので、すばやく血中に取り込まれます。
本来脳には「血液脳関門」があって、不要な物質は脳に入らないように作られています。
しかし、上述のリーキーガット状態にあると、連動して脳のフィルター機能も破壊されやすいことが分かってきました。
その理由の一つは、腸の炎症によって出てくる「上皮細胞の結合をゆるめる物質」が血液に乗って脳にも作用するからです。
このような状態では、たくさんのグルタミン酸を摂取すると、脳にも多量に移行して、脳にダメージを与えてしまいます。
グルタミン酸は有名な「GABA」と深い関係にあるので、グルタミン酸の過剰な摂取で、GABAとのバランスが崩れ、言語能力をはじめたとした脳の機能に大きく影響を及ぼします。
化学調味料を極力控えて、外食や加工品の摂取を減らしましょう。
4)砂糖・人工甘味料
砂糖はいいことはありません。
その理由は・・・
*血糖値の乱高下:自律神経の乱れ、免疫低下、腸内細菌叢の乱れ。
*タンパク質と結びついて「糖化」する:酵素もタンパク質なので、その機能が阻害される。
*インスリン分泌を促す:インスリンは炎症を起こす作用が強い。
*依存性が強い:やめられなくなり悪循環する
5)その他避けるべきもの
*多すぎる乳製品
*プラトレーに熱いものを入れること
*農薬・殺虫剤
*遺伝子組み換え食品
*着色料・発色料
*加工品・レトルトの長期保存品:ハム、ウインナー
*果糖・ブドウ糖液
*人工甘味料:アルパルテーム・スクラロース・アセスルファムカリウムなど
色々考えるときりがありませんが、ざっくり次のようにまとめられます。
①野菜、果物、穀物、豆類、海藻、種子、魚介、肉 などをバランスよく。
葉物野菜も葉酸たっぷりでおすすめ。
②小麦は控えめに。
③化学調味料はやめる。
④砂糖はできるだけゼロに。
⑤加工品、人工甘味料は控える。
「ごはん、野菜たっぷりの味噌汁、焼き魚、豆や昆布の常備菜、デザートはみかん」
こんなイメージですね。
たしかに30年前の日本の食事は、こんな感じだったかもしれません。
子どもたちの脳の育ちと食の関係をちょっと見直してみましょう。
<流行っている病気>
①インフルA
②ウイルス性胃腸炎:ノロ、アデノ
③コロナ
④アデノウイルス:咽頭、目