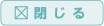★せっかく暖かくなったのに、今日は真っ白!
このお天気の乱高下にはついていけません。
今日2月22日は「猫の日」だそうですね。
ネコ派のかた、今日は猫ちゃんに大サービスしてあげてください。
ところで我が家はわんこ飼い。
犬の日は11月1日とのことですね。(「わんわんわん」から)
ちなみに11月11日は「わんわんギフトの日」だそうです。
8年前から人生初のペット飼いを始め、おうちは汚されましたが、夫婦2人の生活から、オキシトシンたっぷりの別世界が拓けました。
子育てが一段落なさったら、ペット飼いもおすすめですよ~
★さて最近の感染症状況です。
インフルはこのところB>Aの状況です。
小学校中心に、学級閉鎖が続いています。
年が明けてからは、きっとお子さんたち、学校に行った日とお休みした日が同じくらいというかたもおられるのではないでしょうか?
コロナでせっかく普及したリモート授業は活用されないようですね。
★コロナは静かに流行しています。
幸い「昨夜発熱したけど今朝は平熱」程度のお子さんもおられますが、油断はできません。
統計的には、もし脳炎になった場合は、インフルよりも難治性のタイプが多いとの報道もありました。
しっかりマスクして、予防できるものは予防しましょう。
感染は食事時に起きやすいですから、向かい合っての食事は、集団生活では控えたほうがいいでしょう。
★そのほか、アデノ、溶連菌、胃腸炎が目立ちます。
感染しても発症しない基礎的免疫力アップも大切です。
睡眠、栄養、保温・・・
基本はどの病気も共通です。
★私は乳児健診で「静寂は脳のごちそうです」と、いつもお伝えしています。
乳幼児の脳の発達には感覚刺激を集中力をもって受け取ることが大切なので、「聴くともなくついているテレビ、ラジオ、CD」などは、できるだけストップしましょうと、ご説明しています。
さて私は精神科医の樺沢紫苑先生のご著書が大好きです。
その先生のご本で「ぼ~っとしている時間の大切さ」について詳しく述べられていましたので、そこも踏まえて、再度お伝えしようと思います。
ところで、子どもたちの学習成績とスマホ利用について、東北大学と仙台の教育委員会が行った統計があります。
子どもたちがスマホに首ったけで、勉強時間が少なくなるので成績が下がるというのは当然ですが、この統計は、勉強時間を揃えて、スマホ・LINEの利用の有無で比較したデータです。
結果ですが・・・
もちろん勉強時間を同じくして(30分未満・30分以上2時間未満・2時間以上)比較しています。
どのグループでも、スマホ時間が1時間増えるごとに、数学・算数の点数が5点下がったとのことです。
また2時間以上勉強しているグループでも、LINEを4時間以上すると、成績が著しく下がるとのことでした。
その原因として、スマホ使用が次のような脳の状況を引き起こすからだと言われています。
*ワーキングメモリーを低下させる。
*脳疲労を起こす。
*考える機能、記憶する機能が退化する。
成人領域では「スマホ認知症」という言葉があるくらいです。
実際、30~50代でスマホ認知症になったひとは、20~30年後に本物のアルツハイマー病を発症する可能性が高いと言われています。
スマホ認知症において脳の中でどんな状況が生じているか考えてみましょう。
たしかにスマホにはニュースや特ダネネタが溢れています。
とてもこれば便利です。
しかしこれらの便利な情報も、過剰にインプットされることで、脳が「情報のゴミだめ」となってしまい、脳内の情報をうまく取り出せない状態になります。
その結果、記憶力、集中力、思考力、判断力、感情コントロール力、ワーキングメモリーなど、脳のとても重要な機能が著しく低下してしまうのです。
よくよく考えれば、誰と誰が離婚した浮気したなどの特ダネは、自分の生活には何も関係ありませんし、政治や経済のお話をちょっと早く知ったところで、どうにもなりません。
役立つのはお天気と地震速報くらいですね。
せっかくの朝のスッキリ頭を、くだらない情報のインプットでかき乱すなんて、すごく損だと思いませんか?
脳も体の一部、しかも最重要の司令塔です。
酷使しすぎれば、コンピューターがフリーズするように、脳もバグってしまうのです。
そのために必要なのが「ボーッとする時間」であると、樺沢先生はおっしゃいます。
近年の脳科学の研究でも、この「ボーッとすることの大切さ」がしっかりと示されています。
私たちがボーッとしているとき、脳の中では、「デフォルトモードネットワーク」が凄まじく稼働しています。
何をしているかというと、過去の経験を整理統合、現在の自分の現状分析、これから起きることのシュミレーションなどです。
いわば、自分のこれからをより良いものにしていくための準備をしながら、脳がスタンバイしているのです。
なんと、この時、脳は通常の活動時の15倍ものエネルギーを使って稼働していると言われています。
それくらい大切な脳の作業なのです。
情報をゲットしたり、ゲームで楽しんだりすることは、いわば「インプット作業」です。
これに対して、物事を深く創造的に考えることは「アウトプット作業」です。
このアウトプットは、人間だけが脳の前頭前野をフル活動させて行うことができる大切な脳の働きです。
「ボーッと時間」が不足して、デフォルトモードネットワークが稼働する時間が少ないと、この創造的アウトプットが、上手く出来なくなってしまいます。
私たち大人は、静寂な時間が流れると、なんとなく「音寂しい」ような気がして、テレビやラジオをつけたり、CDを流したりします。
しかしそればかりでは、脳はインプット過剰となって、デフォルトモードネットワークが働く暇がありません。
子どもたちでも同様です。
テレビゲームなどで、ひっきりなしにインプット作業が続くと、子どもたちの脳は脳疲労の極致となりますから、前頭前野を働かせて創造的に集中力を働かせることも困難になるということです。
まさに「静寂は脳のごちそう」なのです。
電車通勤のパパ、ママは、電車の中ではぜひ「ボーッと時間」を過ごしてください。
「ボーッと時間」の過ごし方に慣れたら、その時間で「ひとり会議」を行ってみましょう。
*今度のプレゼンの構想
*最近のうちの子の様子と問題点
*最近の我が家の食生活の反省と改善点
そんな議題はいかがでしょう。
残念ながら私は車通勤なので、「ボーッと時間」にすることはできませんが、お風呂タイムなどは恰好の「ひとり会議」時間です。
議題は、
*外来や病児保育の問題点や改善方法
*指導箋のアイディア
などでしょうか?
マインドフルネスなどの瞑想時間もすごくいいと思います。
*仏教の座禅、
*キリスト教の黙想、
それぞれの文化の中で「静寂を過ごす」アイディアは、しっかりと築かれてきたのですね。
思い起こせば、私の幼稚園時代、おやつを頂く時は、園児みんなが目をつぶって両手を合わせてお皿状にして、その中に先生がひとりひとりおやつを入れてくださったことが思い起こされます。
この時間が、私にとってのいちばん強く印象に残っている幼稚園時代の場面です。
このひとときがまさに瞑想時間だったのですね。
生活の場面での基本状態は静寂であるというイメージを頭の隅に入れて、「音寂しさ感覚」をちょっと遠ざけてみましょう。
家族が揃ってご飯をいただく前に、1分間でもよいので黙想するひとときを作ってみるのもいいかもしれません。
視覚聴覚のインプットを遮断して静寂を作ること、このひとときが人間ならではの前頭前野の活動にとても大切だということを、ぜひ意識してみてください。
<流行っている病気>
①インフルB>A
②溶連菌
③アデノウイルス
④コロナ
⑤胃腸炎